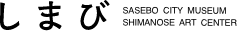7月17日(月・祝)14:00から「森。こだまの前に ~内なる森の交錯~」の関連イベントが行われました。
会場には、異色のメンバーがしまびに初集結。言語学者(ムラブリ族研究者)、肉態表現家、火縄銃専門家、葉っぱのコレクター、ニホンミツバチ研究家、自然派陶芸家、パウル・クレー的アーティストのみなさまです。トークイベント、ムラブリ・ドームの組み上げ説明、舞踏と、高密度で話題満載の1時間でした。
まず最初に、トークイベントでは、絵画出品者の村松信博氏と副嶋志保氏、陶芸展示の江口朋子氏、言語学者の伊藤雄馬氏(ムラブリ族研究者)、火縄銃など色々なメカの修復をしている野元浩二氏、そして、本展企画者の平田雄志氏、計6名による専門分野の見地からの説明後、お客様から質問が飛び交いました。
メカニックに携わる野元氏に「大抵のモノは直すことができる」と。野元氏は火縄銃の管理責任者の免許を取得しており、火縄銃の手入れや修復等も手掛けています。
言語学者の伊藤雄馬氏には、少数民族ムラブリ族の生活についての質問がありました。「ムラブリ」とは彼らの言葉で「森の人」という意味です。ムラブリ族は文字を持たず、今日や明日といった暦の概念もなく、何か予定を一緒に仲間で計画しようと思っても集まることがないそうです。日本人には考えられないシンプルな生活です。
次に「ムラブリドーム」の組み上げについて、伊藤氏が解説。ドームは、木の板、挟むためのクリップ、糸を組み合わせて簡単に作れます。糸の引っ張る力ととどまる力を利用して自立します。実際に建っているドームに入って体験をした人は「いつも見ているしまびのロビーが三角形になって不思議だ」、「中は狭そうに見えたが入ってみると意外と広い」と驚きの連発です。「食べること」と並んで生きるために必要な「寝ること」を確保するために、すぐに作れる寝場所です。
最後に、山下洋輔氏と「肉態即興DUO」を15年近くされている肉態表現家、戸松美貴博氏が「森」や「こだま」を表現したパフォーマンスを披露されました!伊藤氏のバンドネオンに合わせてパフォーマンスをする姿に、来場者のみなさまは何かにとりつかれたようでした。
今回のイベントで、人間は、食べる、寝るというシンプルな生活で生きていけるということに気づかされました。そこに絵画、工芸、踊りなどの芸術があれば、心が豊かになると。お金を必要としないムラブリ族の生き方を知ることは、私たち日本人の生き方を再考する機会となったのではないでしょうか。1階ロビーには文化や歴史に敏感でパワフルなお客様が集まりました。終了後も閉館ぎりぎりまで質問や意見交換が続きました。企画者、出展者、鑑賞者がしまびで出会い、繋がっていく、これぞ、しまびでやりたいことです。
企画者の平田雄志さんに脱帽です。みなさま、ありがとうございました。
(写真協力(一部):林田聡)
#しまび #佐世保市博物館島瀬美術センター #佐世保市 #伊藤雄馬 #野元浩二 #戸松美貴博 #江口朋子 #平田雄志 #ムラブリ #ムラブリドーム #ニホンミツバチ #葉っぱのコレクション #言語学者



 (写真協力:林田聡)
(写真協力:林田聡)

申し訳ございません。空調不良のため、本日のミュージアム・コンサート祭りは、お客様、出演者のみなさまにたいへんご迷惑をおかけしました。昨日のイベント時に発覚、急ぎ、扇風機を運び入れましたが、空調機は回復せず、本日はスポットクーラーと扇風機で対応させていただきました。
第1部は、新都山流大師範 門屋尚山(尺八)、ラスティ・ブレヴィンズ(サクソフォン)、サチ・ブレヴィンズ(フルート、ピアノ)、奥永紀子(ピアノ)のみなさまによる演奏。全米木管楽器コンクール・ジュニア部門(11〜14才)で金賞を受賞したSachiさんのフルート、お父様のサクソフォン、不思議と合う尺八、ピアノとのハーモニーは抜群でした。
第2部は、松尾俊哉(歌)、松尾真弓(ピアノ)のお二人による演奏でした。会場にバリトンの声が響きわたるとお客様の視線が一気に集中。森をテーマにしたイタリア歌曲は、深緑の森林がイメージできました。「見上げてごらん夜の星を」では会場のお客様と大合唱となり、盛りあがりました。
暑く、熱く盛りあがったしまびの「ミュージアム・コンサート祭り」、ご来館いただいたお客様、出演者のみなさま、ありがとうございました。




明日7月17日(月・祝)14:00からは「森、こだまの前に。〜内なる森の交錯〜」関連イベントを開催します。たいへん貴重な機会です。みなさまのご来館をお待ちしております。暑さ対策もよろしくお願いします。
●出展者トーク
●言語学者・伊藤雄馬 ワークショップ「ムラブリドーム」の組み上げ
●伊藤雄馬&戸松美貴博による舞踏
文字がない森の中を移動しながら生活する狩猟採集民「ムラブリ」の言語を15年以上を研究している。2022年ドキュメンタリー映画「森のムラブリ」(監督:金子遊)に出演。現地コーディネーター、字幕を担当。初著作2023年『ムラブリ』(発行:集英社インターナショナル)。ムラブリ研究の一つとしてモバイル型DIY「ムラブリドーム」を発明。島根県出身。定住していない。
25年以上、精神医療や福祉でプログラム講師(呼吸ワーク、即興コミュニティダンス、自由アート創作など)を続けながら、肉躰の塊の態度で「肉態」と独自の身体表現を行なう。12年以上、
山下洋輔との肉態DUOも続く。TokyoExperimental特別賞。2021年『肉態問答』主演。
・副嶋志保(アーティスト)
1994年生まれ。蟹座、O型。長崎県佐世保出身。好きな言葉は「艮為山」。
1990年生まれ。双子座、AB型。長野県出身、京都在住。
・野元浩二(二ホンミツバチ研究家)
佐世保出身。車・バイク・自転車・古式銃などメカの修理に堪能。
1949年東京生まれ。1978年に 「松聲館道場」を設立。以来、独自に剣術、体術、杖術などの研究に入る。2000年頃からその技と術理がスポーツや楽器演奏、介護、ロボット工学や教育などの分野からも関心を持たれている。著作・講習会、多数。
佐世保出身、ニホンミツバチの講習会、武術/身体の講習会、ライブ、映画上映など主に佐世保で企画開催。平田整骨院院長。
本日7月15日(土)から「ミニチュアベーカリの世界展2023 in佐世保 」と「西本喜美子写真展~もっと遊ぼかね!~」が始まりました!
当館の開館時間は10:00ですが、8:00頃から既に並んでいるお客様もいらっしゃって、展覧会への期待感が伝わってきました。
11:35から13:00まではNIB長崎国際テレビのバラエティ番組「ひるじげドン」が生中継!安田館長が「ミニチュアベーカリの世界展2023 in 佐世保」と「西本喜美子写真展~もっと遊ぼかね!~」の概要や見どころなどを紹介しました。ミュージアム・ショップでは既に残りわずかになった商品もあったほど人気で、すぐにスタッフが追加注文をしていました。
14:00からは「西本喜美子写真展」の関連イベントで、西本喜美子氏、西本和民(かずたみ)氏、安田館長の3人によるトークイベント、15:00からは西本和民氏による写真講座が行われました。
西本喜美子氏は西本和民氏が塾長をする写真塾で受講生として参加して自由に楽しく撮っているとお話をしていました。
また、西本和民氏の写真講座も行われ、来館された方は熱心に聞いていました。
ご遠方から駆けつけてくださった西本喜美子さん、和民さん、優美塾のみなさま、そして暑い中ご来館いただいたお客様、ほんとうにありがとうございました。







6/21(水)14時から、岩手県大船渡市出身のシンガーソングライター濱守栄子さんと未来アーティストたっちさんの“ももしまライブ”が行われました。これは、6/21(水)から1階フリースペースにて開幕した「第5回心からこころへの絵手紙展 人々に幸せが届きますように」(主催:谷口和子氏)の関連イベントです。
濱守栄子さんとたっちさんのお二人は現在、日本一周をしながら「1000人の大人の夢」を加速させるプロジェクトとして、
①夢を追いかける大人が増えることで、日本を元気にする。
②夢を持つ大人が増えることで子どもたちに希望を与える。
③収益の一部を東日本大震災で被災した大船渡市と陸前高田市のために使用する。
といったことを目的に全国を周っています。そのプロジェクトの中でしまびを訪ねられ、「第5回心からこころへの絵手紙展 人々に幸せが届きますように」関連イベントとして企画されました。グッドタイミングです!
テーマである「1000人の大人たちの夢を加速させる」については、世界各国で、子どもたちが大人を尊敬しているかアンケートをとったところ、日本が約20%ぐらいしかいなかった事実に驚き、考えたもの。子どもたちが大人を尊敬できるようになってもらいたい、そのためには、大人たちに夢をもってもらいたい、その夢を実現するには夢を語ること、書くこと、期限を決めることが必要だと話されました。
演奏は、主にふるさと岩手を思いだされるような曲を中心に行われました。そのうちの一曲「国道45号線」は、岩手県トラック協会CMソングとして採用され、知られています。他にも、オリジナル曲「キセキ」では手話を交えながら、「あの大船渡」では震災前の風景が忘れられてしまっていたエピソードの紹介のあと、歌われました。その曲を聴き、思わず涙が出るほど心に響く演奏でした。
ご来館いただいたお客様、そして、濱守栄子さん、たっちさん、ありがとうございました!






6/18(日)13時に画家木本和幸氏によるギャラリートークが中2階ギャラリーで行われ、16名の来場者が訪れました。
木本氏は幼少期から絵に親しみ、高校在学中には公募展にも入賞されました。東京藝術大学卒業後は、大学非常勤講師、高等学校美術教諭など様々な美術教育の場で長年ご活躍されてきました。
ギャラリートークでは、木本氏は命や意識というのは光だ、光なしでは人は生きていくことはできないと語られ、タイトルにある「光と命のエネルギー」のテーマに沿って作品解説を行われました。解説に来場者は熱心に耳を傾けており、構図の配置、筆の太さ、どうしてこの色にした、絵を描くにあたって注意したことなどの質問にも木本氏は真摯に答えられていました。
今回の展示には、油絵、シルクスクリーン、水彩画、そして、新たな取り組みとしてデジタルアートがありました。特にデジタルアートはエネルギーの根源である人間の意識を想像させる作品であり、見ているとエネルギーがみなぎってくるようでした。






ミュージアム・コンサートを開催しました。
今回は、「世界文化遺産 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 登録5周年記念 セレクション・コレクション 祈りの世界展」に合わせ、“祈り”をテーマに演奏。新型コロナウィルス感染症5類感染症移行後、念のためゆっくりめに椅子を設置していましたが、14:00開演近くになると、みるみるお客様が集まって満席となり、椅子を追加するほどでした。
まず、ブレヴィンズ幸さんによるピアノの独奏からスタート。幸さんは日野中学校に体験入学中の中学3年生。15歳とは思えない落ち着いた演奏でドビュッシーのアラベスク1番を披露しました。
次にお父様のラスティ・ブレヴィンズさんによるサクソフォンと幸さんのピアノによるアリア(ボザ)、白鳥(サン=サーンス)でお客様を魅了しました。ラスティ・ブレヴィンズさんは、ラスベガス在住のサックス奏者で、ハウステンボスでの演奏をきっかけに何度も来日しています。
イマージュ (ボザ)では幸さんがフルートのソロ。吹き抜けの空間に心地よい音色が響きわたりました。
さらに、門屋尚山さんの尺八が加わり、アヴェ・マリア(シューベルト)をトリオで演奏。日本と西洋が融合した不思議な音の世界に、会場が包まれていました。門屋尚山さんは平戸在住。新都山流大師範です。平成13年民謡夢舞台で原田直行氏の伴奏、平成21年オランダ大使夫妻&第41代松浦家ご夫妻のディナータイムショーなどで演奏経験豊富なかたです。
アンダンテとスケルツォ(ガンヌ)では、奥永紀子さんの伴奏に合わせ、幸さんがフルートを奏で、お客様の視点が2人に集中していました。
拍手が鳴りやまず、アンコールの赤とんぼでは、のどかな日本の原風景を感じさせました。
ご来館いただいたたくさんのみなさま、演奏者のみなさまありがとうございました!好評につき、来月7月16日(日)も同じメンバーでミュージアム・コンサートを実施することにいたします!!14:00開演、観覧無料です。来月も、ぜひぜひぜひ、お越しください。
[出演者]
・新都山流大師範 門屋尚山(尺八)
・奥永紀子(ピアノ)
・ラスティ・ブレヴィンズ Rusty Blevins(サクソフォン)
・幸ブレヴィンズ Sachi Blevins(フルート)
[プログラム]
・Arabesque No.1- Debussy
・Aria – Bozza
・The Swan -Saint saens
・Image – Bozza
・Ave Maria – Schubert
・Andante et Scherzo – Ganne
・赤とんぼ- 山田耕筰







5月28日(土)14時に第56回佐世保美術展 ART WAVE FROM THE WESTの オーディエンス賞表彰式を行いました!
オーディエンス賞に選ばれたのは彫刻・工芸部門に出品された山口隆介さん! 作品は《Hybrid(雑種)》。
山口さんは今回が3回目の出品。シリコンを素材にまち針を使って長い髭を1本1本丁寧に作ったり、週末しか制作時間がとれず子どもたちを寝かせてから深夜2時~3時頃に制作を続けたそうです。
作品に投票した人からは、「リアルすぎる!!」、「異色だが、細い」、「アイデアが面白い」といった感想が多く見られました。
山口さんには公益財団法人佐世保地域文化事業財団の永元理事長より記念の盾と賞状が贈られました。
おめでとうございます!





28日(土)13:30に第48回長崎県書道展の解説会が行われ、たくさんの方がご来館されました!
4人の先生方による解説に、来館者された方々は熱心に耳を傾けて清聴されていました。
コロナ禍の中、長崎県書道展は中止になることがなく続けられたのは熱心な先生方と書に関われる方々の情熱の成果であることを実感する解説会でした。





本日14時、1階ロビーでミュージアム・コンサートが行われました。こちらは4月29日(土)から5月4日(木)まで2階展示室で開催中の「みぞかみつよしの POP STEP 展」の関連イベントです。
みぞかみつよしさんは佐世保市在住のアーティストで、小さい頃から絵を描くことが大好きだったそうです。今回、島瀬美術センターでは主に絵画を展示しており、制作したものには来館された方が思わず目を丸くする作品が大集結しています。また、みぞかみさんは佐世保市民展(現:佐世保美術展)で数々の賞を受賞されました。
14時から14時30分まで 音楽サークル コンアモーレ のみなさまが演奏しました。その中に「みぞかみつよしの POP STEP 展」主催の みぞかみさん も一緒に演奏されていました。
14時30分から15時まではJelly fish のお二人による演奏がありました。お二人のシンセサイザーでの演奏を来館者は熱心に耳を傾けていました。
本日はお足元の悪い中、館内で演奏いただきましたみなさま、ご来館いただきましたみなさま、誠にありがとうございます。








 (写真協力:林田聡)
(写真協力:林田聡)